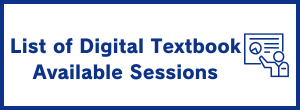概要
展示会場入場に必要な来場登録とは連動しておりません。
カンファレンス申込みとは別に来場登録も事前にお済ませの上、ご来場ください。
講演情報については順次更新いたします。

|
積水化学工業(株) 代表取締役社長 加藤 敬太 |

|

【講演内容】
積水化学工業は、次世代の革新的エネルギー技術として、独自技術が詰まったフィルム型ペロブスカイト太陽電池の実用化を推進しています。本講演ではその開発状況と、軽量・柔軟性を活かした特長による新たな展開、持続可能な社会実現に向けた可能性について講演します。
【講演者プロフィール】
1980年3月、京都大学工学部を卒業後、積水化学工業に入社。中間膜の技術開発に従事した後、アメリカ・ドイツでの駐在で現地工場長や事業会社社長を経験。その後06年より中間膜事業部長を務め、グローバルで存在感を持ち全社を牽引する事業へと飛躍的に成長させる。08年執行役員に就任後は、新事業推進部長、開発研究所長等を歴任。イノベーションによる新製品開発、新規市場開拓を強力に推進し、同社の事業領域拡大に寄与。
14年から取締役 高機能プラスチックスカンパニープレジデントとして、積水化学グループの最高益更新に貢献。19年からの代表取締役 経営戦略部長を経て、20年3月代表取締役社長に就任し、現在に至る。
【講演内容】
積水化学工業は、次世代の革新的エネルギー技術として、独自技術が詰まったフィルム型ペロブスカイト太陽電池の実用化を推進しています。本講演ではその開発状況と、軽量・柔軟性を活かした特長による新たな展開、持続可能な社会実現に向けた可能性について講演します。
【講演者プロフィール】
1980年3月、京都大学工学部を卒業後、積水化学工業に入社。中間膜の技術開発に従事した後、アメリカ・ドイツでの駐在で現地工場長や事業会社社長を経験。その後06年より中間膜事業部長を務め、グローバルで存在感を持ち全社を牽引する事業へと飛躍的に成長させる。08年執行役員に就任後は、新事業推進部長、開発研究所長等を歴任。イノベーションによる新製品開発、新規市場開拓を強力に推進し、同社の事業領域拡大に寄与。
14年から取締役 高機能プラスチックスカンパニープレジデントとして、積水化学グループの最高益更新に貢献。19年からの代表取締役 経営戦略部長を経て、20年3月代表取締役社長に就任し、現在に至る。
<モデレーター>

|
(株)たすきづな 代表取締役 柳原 直人 |

|

<パネリスト>

|
旭化成(株) デジタル共創本部インフォマティクス推進センター シニアフェロー 青柳 岳司 |

|


|
国立大学法人京都大学 大学院理学研究科化学専攻 教授 副プロボスト 理事補(企画・調整担当) 北川 宏 |

|


|
(株)Preferred Networks 共同創業者 代表取締役 最高技術責任者 最高研究責任者/(株)Preferred Computational Chemistry 代表取締役社長/(株)Preferred Elements 代表取締役社長 岡野原 大輔 |

|

【講演内容】
マテリアルズインフォマティクス(MI)は革新的材料の開発において起爆剤になることが期待されている。本講演ではアカデミア、スタートアップ、大手化学企業で革新的材料の開発に関わる第一人者をお招きし、①MIの現状と、②MIの革新的材料開発への応用や期待されるシナジーについて意見交換を行う。
【講演者プロフィール】
●柳原 直人 氏
1986年4月、京都大学化学系を修了、富士フイルム(株)に入社。以後、2015年まで材料系研究者を経て研究所長、技術戦略部長を歴任。2015年以降、取締役・常務執行役員としてR&D統括本部長、先端技術やバイオの研究所長、知的財産本部管掌を歴任。2024年9月、富士フイルムを退職、現在に至る。
●青柳 岳司 氏
1987年3月、京都大学薬学研究科博士前期課程修了。同4月、旭化成工業(株)入社、主に材料シミュレーションに従事。2002年9月 名古屋大学にて博士(工学)取得。
2016年5月 (国研)産業技術総合研究所入所。NEDOプロなど、材料シミュレーションおよびインフォマティクス研究に従事。
2022年7月 旭化成(株)入社 プリンシパルエキスパート、センター長を経て2024年10月より現職
●北川 宏 氏
1986年、京都大学理学部卒業。1991年、同大学院理学研究科博士後期課程を単位取得退学、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所助手。1992年、博士(理学)学位取得。1993年英国王立研究所訪問研究員、1994年、北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科助手。2000年、筑波大学化学系助教授。2003年、九州大学大学院理学研究院化学部門教授。2009年より、京都大学大学院理学研究科化学専攻教授。京都大学副プロボスト、理事補(企画・調整担当)を兼務。2021年から、科学技術振興機構CREST研究総括「未踏探索空間における革新的物質の開発」。趣味は飲み歩き。
●岡野原 大輔 氏
2010年に東京大学にて博士(情報理工学)取得。大学院在学中の2006年に、西川徹等とPreferred Networks(PFN)の前身となる株式会社Preferred Infrastructureを創業。2014年3月に深層学習の実用化を加速するためPFNを創業。現在はPFNの最高技術責任者、最高研究責任者として、基盤モデルの研究開発などに取り組んでいる。PFNとENEOSが共同開発した汎用原子レベルシミュレータMatlantisの販売を行う株式会社Preferred Computational Chemistry、生成AI基盤モデルの開発を行う株式会社Preferred Elementsの代表取締役社長を兼任。受賞歴、著書多数。
【講演内容】
マテリアルズインフォマティクス(MI)は革新的材料の開発において起爆剤になることが期待されている。本講演ではアカデミア、スタートアップ、大手化学企業で革新的材料の開発に関わる第一人者をお招きし、①MIの現状と、②MIの革新的材料開発への応用や期待されるシナジーについて意見交換を行う。
【講演者プロフィール】
●柳原 直人 氏
1986年4月、京都大学化学系を修了、富士フイルム(株)に入社。以後、2015年まで材料系研究者を経て研究所長、技術戦略部長を歴任。2015年以降、取締役・常務執行役員としてR&D統括本部長、先端技術やバイオの研究所長、知的財産本部管掌を歴任。2024年9月、富士フイルムを退職、現在に至る。
●青柳 岳司 氏
1987年3月、京都大学薬学研究科博士前期課程修了。同4月、旭化成工業(株)入社、主に材料シミュレーションに従事。2002年9月 名古屋大学にて博士(工学)取得。
2016年5月 (国研)産業技術総合研究所入所。NEDOプロなど、材料シミュレーションおよびインフォマティクス研究に従事。
2022年7月 旭化成(株)入社 プリンシパルエキスパート、センター長を経て2024年10月より現職
●北川 宏 氏
1986年、京都大学理学部卒業。1991年、同大学院理学研究科博士後期課程を単位取得退学、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所助手。1992年、博士(理学)学位取得。1993年英国王立研究所訪問研究員、1994年、北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科助手。2000年、筑波大学化学系助教授。2003年、九州大学大学院理学研究院化学部門教授。2009年より、京都大学大学院理学研究科化学専攻教授。京都大学副プロボスト、理事補(企画・調整担当)を兼務。2021年から、科学技術振興機構CREST研究総括「未踏探索空間における革新的物質の開発」。趣味は飲み歩き。
●岡野原 大輔 氏
2010年に東京大学にて博士(情報理工学)取得。大学院在学中の2006年に、西川徹等とPreferred Networks(PFN)の前身となる株式会社Preferred Infrastructureを創業。2014年3月に深層学習の実用化を加速するためPFNを創業。現在はPFNの最高技術責任者、最高研究責任者として、基盤モデルの研究開発などに取り組んでいる。PFNとENEOSが共同開発した汎用原子レベルシミュレータMatlantisの販売を行う株式会社Preferred Computational Chemistry、生成AI基盤モデルの開発を行う株式会社Preferred Elementsの代表取締役社長を兼任。受賞歴、著書多数。

|
金沢工業大学 革新複合材料研究開発センター 教授・顧問 小田切 信之 |

|

【講演内容】
1990年代、米国の産業界は、垂直統合から水平分業へ転換。これにより、産/学間の人材流動が一気に加速した。強くなった米国の大学の現状を眺めます。
【講演者プロフィール】
1981年早稲田大学大学院修了。東レ㈱に入社。炭素繊維複合材料の研究開発に従事したのち、米国シアトル近郊の研究・開発・製造拠点で工場運営とプロジェクト管理に従事(計16年)。2024年金沢工業大学・革新複合材料研究開発センター(現職)。工学博士(2021年)。SAMPE(先端材料技術協会)フェロー。
【講演内容】
1990年代、米国の産業界は、垂直統合から水平分業へ転換。これにより、産/学間の人材流動が一気に加速した。強くなった米国の大学の現状を眺めます。
【講演者プロフィール】
1981年早稲田大学大学院修了。東レ㈱に入社。炭素繊維複合材料の研究開発に従事したのち、米国シアトル近郊の研究・開発・製造拠点で工場運営とプロジェクト管理に従事(計16年)。2024年金沢工業大学・革新複合材料研究開発センター(現職)。工学博士(2021年)。SAMPE(先端材料技術協会)フェロー。

|
東レ(株) 化成品研究所 樹脂研究室 研究主幹 小林 定之 |

|

【講演内容】
二種類の高分子について、ナノオーダーで精密制御された三次元的な連続構造を形成させ、均一な構造となることにより、両方の高分子の特性が最大限に活かされ、従来技術では実現不可能だった革新材料の実現が初めて可能となった。
【講演者プロフィール】
1995年3月 東京工業大学大学院卒業。東レに入社。化成品研究所に所属し、一貫してポリマーアロイ技術開発研究に従事。2022年に、ポリマーナノアロイに関し、日本化学会技術賞を受賞し、同年、東レリサーチフェローに就任し、現在に至る。
【講演内容】
二種類の高分子について、ナノオーダーで精密制御された三次元的な連続構造を形成させ、均一な構造となることにより、両方の高分子の特性が最大限に活かされ、従来技術では実現不可能だった革新材料の実現が初めて可能となった。
【講演者プロフィール】
1995年3月 東京工業大学大学院卒業。東レに入社。化成品研究所に所属し、一貫してポリマーアロイ技術開発研究に従事。2022年に、ポリマーナノアロイに関し、日本化学会技術賞を受賞し、同年、東レリサーチフェローに就任し、現在に至る。

|
(株) 東レリサーチセンター 構造化学研究部 部長 関 洋文 |

|

【講演内容】
半導体デバイスの微細化や3次元化が進行しており、それに対応できる分析技術の開発が重要となっています。本講演では、分光分析を中心に、弊社が保有する先端分析技術とその応用例について紹介します。
【講演者プロフィール】
2000年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程卒業。株式会社東レリサーチセンター入社。 主に半導体材料の分光分析に従事。2020年4月より現職。
【講演内容】
半導体デバイスの微細化や3次元化が進行しており、それに対応できる分析技術の開発が重要となっています。本講演では、分光分析を中心に、弊社が保有する先端分析技術とその応用例について紹介します。
【講演者プロフィール】
2000年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程卒業。株式会社東レリサーチセンター入社。 主に半導体材料の分光分析に従事。2020年4月より現職。

|
京都大学 大学院 工学研究科 特定准教授 島野 哲 |

|

【講演内容】
本講演では、住友化学が大学との連携で開発した柔軟な固体電解質により高容量・軽量化の実現を目指す「柔固体型電池」と、低環境負荷、低コストの材料循環を目指す正極材の「ダイレクトリサイクル」について紹介し、実用化に向けた課題と展望を述べる。
【講演者プロフィール】
博士(工学)。
2005年、産業技術総合研究所に入所。電池材料の電解質や正極材の研究開発に従事。
2008年、住友化学株式会社に入社。リチウムイオン二次電池用正極材の開発に従事。正極材のダイレクトリサイクルを提案し、技術開発を開始。
2020年、京都大学固体型電池システムデザイン産学共同講座の特定准教授に着任。柔固体電池とダイレクトリサイクル技術の開発を担当。現在に至る。
【講演内容】
本講演では、住友化学が大学との連携で開発した柔軟な固体電解質により高容量・軽量化の実現を目指す「柔固体型電池」と、低環境負荷、低コストの材料循環を目指す正極材の「ダイレクトリサイクル」について紹介し、実用化に向けた課題と展望を述べる。
【講演者プロフィール】
博士(工学)。
2005年、産業技術総合研究所に入所。電池材料の電解質や正極材の研究開発に従事。
2008年、住友化学株式会社に入社。リチウムイオン二次電池用正極材の開発に従事。正極材のダイレクトリサイクルを提案し、技術開発を開始。
2020年、京都大学固体型電池システムデザイン産学共同講座の特定准教授に着任。柔固体電池とダイレクトリサイクル技術の開発を担当。現在に至る。

|
日本ガイシ(株) 研究開発本部 基盤技術統括部 基盤技術3部 部長 吉川 潤 |

|

【講演内容】
日本ガイシでは、独自の結晶成長法や異種材接合技術を用い、様々な化合物半導体ウエハーを開発している。本講演では、パワーデバイスや高周波デバイス向けに市場拡大が期待されるSiC、GaN、AlN、Ga2O3に関し、弊社でのウエハー開発事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年3月、京都大学大学院工学研究科修了。同年4月、日本ガイシ株式会社に入社。
研究開発本部に所属し、半導体製造装置用セラミック部材等、各種セラミック製品の開発に従事。
2018年より化合物半導体ウエハーの開発を担当し、現在に至る。
【講演内容】
日本ガイシでは、独自の結晶成長法や異種材接合技術を用い、様々な化合物半導体ウエハーを開発している。本講演では、パワーデバイスや高周波デバイス向けに市場拡大が期待されるSiC、GaN、AlN、Ga2O3に関し、弊社でのウエハー開発事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年3月、京都大学大学院工学研究科修了。同年4月、日本ガイシ株式会社に入社。
研究開発本部に所属し、半導体製造装置用セラミック部材等、各種セラミック製品の開発に従事。
2018年より化合物半導体ウエハーの開発を担当し、現在に至る。

|
(国研)産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 機能材料プロセス研究グループ 研究グループ長 阿多 誠介 |

|

【講演内容】
次世代移動通信規格である6Gは、2030年ごろの運用開始が予定されている。その機能は5Gを上回るものであり、それを支えるためのさまざまな材料開発が世界各国で活発に進められている。本講演では、特に基板材料の開発に焦点を当て、産総研における取り組みや将来ビジョンについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2010年3月東京工業大学大学院修了、2010年4月、国立研究開発法人産業技術総合研究所入所。CNTの複合材料開発に10年ほど従事。2019年〜2020年、Fraunhofer IPA研究所滞在研究員。2021年より低誘電基板材料研究に従事し現在に至る。
【講演内容】
次世代移動通信規格である6Gは、2030年ごろの運用開始が予定されている。その機能は5Gを上回るものであり、それを支えるためのさまざまな材料開発が世界各国で活発に進められている。本講演では、特に基板材料の開発に焦点を当て、産総研における取り組みや将来ビジョンについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2010年3月東京工業大学大学院修了、2010年4月、国立研究開発法人産業技術総合研究所入所。CNTの複合材料開発に10年ほど従事。2019年〜2020年、Fraunhofer IPA研究所滞在研究員。2021年より低誘電基板材料研究に従事し現在に至る。

|
(国研)物質・材料研究機構 高分子系複合材料グループ グループリーダー 内藤 公喜 |

|

【講演内容】
耐熱ポリイミド接着剤と一般的な接着継手を用いて(題材として)接着接合部の力学特性評価手法を示す
【講演者プロフィール】
1998年3月に同志社大学にて「高じん性化エポキシ接着剤の静的および疲労き裂進展特性に関する研究」で博士後期課程修了、2005年2月まで三菱電機株式会社・鎌倉製作所相模工場技術課で人工衛星等の複合材料・接着構造製品の製造設計業務に従事、2005年2月から物質・材料研究機構で研究業務に従事、現在構造材料研究センタ-高分子系複合材料グループのグループリーダー
【講演内容】
耐熱ポリイミド接着剤と一般的な接着継手を用いて(題材として)接着接合部の力学特性評価手法を示す
【講演者プロフィール】
1998年3月に同志社大学にて「高じん性化エポキシ接着剤の静的および疲労き裂進展特性に関する研究」で博士後期課程修了、2005年2月まで三菱電機株式会社・鎌倉製作所相模工場技術課で人工衛星等の複合材料・接着構造製品の製造設計業務に従事、2005年2月から物質・材料研究機構で研究業務に従事、現在構造材料研究センタ-高分子系複合材料グループのグループリーダー

|
ダイハツ工業(株) 生産調達本部 車両生技部 塗装生技室 主担当員 棚橋 朗 |
|
【講演内容】
2022年10月に発足した自動車塗装CN研究会の取り組み・考え方について紹介をしたい。本件2050年までの温室効果ガス排出ゼロ目標を達成する為、「自動車塗装プロセス改革の方向性」についてOEM各社から代表者を排出し取り組んでいる内容であり最新の検討状況・考え方について共有する場としたい。
【講演内容】
2022年10月に発足した自動車塗装CN研究会の取り組み・考え方について紹介をしたい。本件2050年までの温室効果ガス排出ゼロ目標を達成する為、「自動車塗装プロセス改革の方向性」についてOEM各社から代表者を排出し取り組んでいる内容であり最新の検討状況・考え方について共有する場としたい。
OEM8社によるパネルディスカッション
|
|
<モデレーター> トヨタ自動車(株) 塗装成形製造技術部 塗装成形計画室 室長 村田 亘 |
|

|
日産自動車(株) カスタマーパフォーマンス&車両性能技術開発本部 材料技術部 車両材料開発グループ 主担 鈴木 達也 |
|

|
(株)本田技術研究所 材料研究センター モビリティ材料研究開発室 事業革新材料ブロック マネージャー 近藤 益雄 |
|

|
マツダ(株) 技術本部 車両技術部 塗装技術グループ マネージャー 大谷 崇 |
|

|
ダイハツ工業(株) 生産調達本部 車両生技部 塗装生技室 主担当員 車 圭二 |
|

|
(株)SUBARU モノづくり本部 車体生産技術部 車体企画課 課長 仁志 匡宏 |
|

|
三菱自動車工業(株) 生産技術本部 塗装生産技術部 先行技術グループ マネージャー 三宅 正幸 |
|

|
スズキ(株) 生産本部 塗装生産部 塗装材料・解析課 係長 立山 大輔 |
|

|
トヨタ自動車(株) 塗装成形製造技術部 塗装成形計画室 企画戦略グループ 主幹 加藤 大雄 |
|

|
東海大学 学長補佐 政治経済学部 経済学科 教授 細田 衛士 |
|

|
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課(併任) 総務課・廃棄物適正処理推進課 課長補佐 水島 大輝 |
|

|
花王(株) 生産技術センター SCM戦略部 ESG・業務推進部長 野元 秀利 |
|

|
資源循環プロジェクト代表 / 日榮新化(株) 資源循環事業部長 本池 高大 |
|
交流会

|
講演後そのままパーティーに移ります 参加対象者:講師、聴講者全員 参加費:無料 飲み物、 軽食をご用意しております |
|

|
(株)本田技術研究所 材料研究センター モビリティ材料研究開発室 室長 高田 健太郎 |

|

【講演内容】
地球環境と持続可能な社会のために企業の取り組みとしてリソースサーキュレーションは必要不可欠である。欧州を中心にグローバルで再生材利用の規制が加速する傾向にあり、モビリティへの適用は様々な課題がある。商品展開へ向けた課題とお客様への提供価値をどのようにバランスをとり進めるかを考える。
【講演者プロフィール】
1998年3月大阪大学修士課程修了、(株)本田技術研究所に入社、四輪R&Dセンター材料研究部門に所属しエンジン部品材料開発に従事。2020年より本田技研工業(株)にて四輪完成車材料開発を担当し2023年よりBEV開発センター材料開発部にて循環資源・再生材の車両適用に向けて活動。25年4月から(株)本田技術研究所材料研究センターにてモビリティ材料研究開発を担当する。
【講演内容】
地球環境と持続可能な社会のために企業の取り組みとしてリソースサーキュレーションは必要不可欠である。欧州を中心にグローバルで再生材利用の規制が加速する傾向にあり、モビリティへの適用は様々な課題がある。商品展開へ向けた課題とお客様への提供価値をどのようにバランスをとり進めるかを考える。
【講演者プロフィール】
1998年3月大阪大学修士課程修了、(株)本田技術研究所に入社、四輪R&Dセンター材料研究部門に所属しエンジン部品材料開発に従事。2020年より本田技研工業(株)にて四輪完成車材料開発を担当し2023年よりBEV開発センター材料開発部にて循環資源・再生材の車両適用に向けて活動。25年4月から(株)本田技術研究所材料研究センターにてモビリティ材料研究開発を担当する。

|
TOPPAN(株) 生活・産業事業本部 SX推進センター SX事業開発本部 新事業開発推進部、主席研究員 藤井 崇 |
|
|
|
三井化学(株) ICTソリューション事業本部 企画管理部 コンバーティングCoE推進G グループリーダー 宇於崎 浩隆 |
|
|
|
アールエム東セロ(株) 環境経営推進室 室長 根岸 和彦 |
|

|
(株)カネカ CO2 Innovation Laboratory 所長 佐藤 俊輔 |

|

【講演内容】
カネカはプラスチック代替材料として海洋生分解性バイオポリマーの市場投入を進めている。化石資源利用削減、海洋プラスチック問題解決を目指すにあたり、長期的な原料調達、利用技術開発が課題である。現在、CO2を直接炭素源として利用する技術開発を進めている。本講演にて進捗を紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年3月、広島大学大学院卒業。株式会社カネカに入社。入社以来、生分解性バイオポリマーの微生物生産技術、工業生産プロセス開発に従事。
2013~15年、ドイツミュンスター大学 客員研究員(2015年、カネカ復職)
2023年より、NEDO GI基金事業に採択され、研究責任者に就任。
2024年CO2 Innovation Laboratory所長、現在に至る。
【講演内容】
カネカはプラスチック代替材料として海洋生分解性バイオポリマーの市場投入を進めている。化石資源利用削減、海洋プラスチック問題解決を目指すにあたり、長期的な原料調達、利用技術開発が課題である。現在、CO2を直接炭素源として利用する技術開発を進めている。本講演にて進捗を紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年3月、広島大学大学院卒業。株式会社カネカに入社。入社以来、生分解性バイオポリマーの微生物生産技術、工業生産プロセス開発に従事。
2013~15年、ドイツミュンスター大学 客員研究員(2015年、カネカ復職)
2023年より、NEDO GI基金事業に採択され、研究責任者に就任。
2024年CO2 Innovation Laboratory所長、現在に至る。

|
環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室長 兼 リサイクル推進室長 近藤 亮太 |
|
【講演内容】
環境省では2024年8月2日に第五次循環型社会形成推進基本計画を策定しました。2024年7月には初めて「循環経済に関する関係閣僚会議」を設置し、本計画を国家戦略に位置付けるとともに、その実現に向けた具体的な取組を2024年12月に政策パッケージとして取りまとめました。本講演ではこのような政府の最新の動向についてご説明させて頂きます。
【講演者プロフィール】
1998年環境庁入庁。総合環境政策局、地球環境局、廃棄物・リサイクル対策部、中部地方環境事務所等に勤務したほか、原子力規制庁、警察庁、中間貯蔵・環境安全事業株式会社に出向。2023年7月から現職。プラスチック資源循環、第5次循環型社会形成推進基本計画の策定、循環経済への移行等を担当。
【講演内容】
環境省では2024年8月2日に第五次循環型社会形成推進基本計画を策定しました。2024年7月には初めて「循環経済に関する関係閣僚会議」を設置し、本計画を国家戦略に位置付けるとともに、その実現に向けた具体的な取組を2024年12月に政策パッケージとして取りまとめました。本講演ではこのような政府の最新の動向についてご説明させて頂きます。
【講演者プロフィール】
1998年環境庁入庁。総合環境政策局、地球環境局、廃棄物・リサイクル対策部、中部地方環境事務所等に勤務したほか、原子力規制庁、警察庁、中間貯蔵・環境安全事業株式会社に出向。2023年7月から現職。プラスチック資源循環、第5次循環型社会形成推進基本計画の策定、循環経済への移行等を担当。

|
経済産業省 GXグループ 資源循環経済課 課長 田中 将吾 |

|

【講演内容】
近年では、廃棄物問題や気候変動問題に加え、世界的な資源需要と地政学的なリスクの高まりといった資源制約の観点から、サーキュラーエコノミーへの移行が喫緊の課題となっている。本講演では、我が国における資源循環経済政策の最新動向についてお伝えする。
【講演者プロフィール】
東京大学経済学部卒業。平成13年経済産業省入省、29年資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室長、令和2年日本貿易振興機構ベルリン事務所次長兼産業調査員、4年7月より現職。
【講演内容】
近年では、廃棄物問題や気候変動問題に加え、世界的な資源需要と地政学的なリスクの高まりといった資源制約の観点から、サーキュラーエコノミーへの移行が喫緊の課題となっている。本講演では、我が国における資源循環経済政策の最新動向についてお伝えする。
【講演者プロフィール】
東京大学経済学部卒業。平成13年経済産業省入省、29年資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室長、令和2年日本貿易振興機構ベルリン事務所次長兼産業調査員、4年7月より現職。

|
花王(株) 代表取締役 社長執行役員 長谷部 佳宏 |

|

【講演内容】
一般的に、物質の再生には多くのコストとエネルギーがかかるとされています。この常識を覆さなければ、循環型で持続可能な社会の実現は難しいでしょう。
そこで私たちは、「使ったら捨てる」という従来の考え方を見直し、「捨てるものが新たな社会の財産になる」ことを目指した取り組みをご紹介します。
ひとつは、廃棄されるプラスチックを活用し、高耐久な道路を実現する技術。
もうひとつは、廃棄されるレフィル容器を再生し、自由な発想で新たな創造物へと生まれ変わらせる取り組みです。
これらはどちらも、経済的合理性を追求しながら、再生を通じて新たな価値を生み出し、多くの企業が協力してはじめて実現する活動です。
【講演者プロフィール】
1960年生まれ、東京理科大学工学部工業化学科博士課程修了後、1990年4月花王入社。
ビューティケア研究センターヘアビューティ研究所長、基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長、研究開発部門統括、専務執行役員などを経て2021年1月から現職。
【講演内容】
一般的に、物質の再生には多くのコストとエネルギーがかかるとされています。この常識を覆さなければ、循環型で持続可能な社会の実現は難しいでしょう。
そこで私たちは、「使ったら捨てる」という従来の考え方を見直し、「捨てるものが新たな社会の財産になる」ことを目指した取り組みをご紹介します。
ひとつは、廃棄されるプラスチックを活用し、高耐久な道路を実現する技術。
もうひとつは、廃棄されるレフィル容器を再生し、自由な発想で新たな創造物へと生まれ変わらせる取り組みです。
これらはどちらも、経済的合理性を追求しながら、再生を通じて新たな価値を生み出し、多くの企業が協力してはじめて実現する活動です。
【講演者プロフィール】
1960年生まれ、東京理科大学工学部工業化学科博士課程修了後、1990年4月花王入社。
ビューティケア研究センターヘアビューティ研究所長、基盤研究セクター長、エコイノベーション研究所長、研究開発部門統括、専務執行役員などを経て2021年1月から現職。
<モデレーター>

|
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局 事務局次長 柳田 康一 |

|

<パネリスト>

|
アミタホールディングス(株) 執行役員 宮原 伸朗 |

|


|
(株)ヤクルト本社 サステナビリティ推進部資源循環推進課 担当課長 久保 昌男 |

|


|
神戸市 環境局資源循環課 課長 井関 和人 |

|

【講演内容】
CLOMAはプラスチックの循環利用を推進しコミュニティや生活者とともに海洋プラごみのゼロ化を目指す企業アライアンスです。
セミナーでは神戸市にも参加してもらい、同市が進めるプラ回収に参画する企業との議論を通して官民連携の勘所や未来像につき議論を深めます。
【講演者プロフィール】
●柳田 康一 氏
1985年花王株式会社入社、加工プロセス研究室長、包装容器研究室長、サステナビリティ推進部長、ESG部門副統括を歴任、2019年からはCLOMA技術統括を担当し現在に至る。
専門分野は、トイレタリー製品の設計・製造、ユニバーサルデザイン、レスポンシブルケア、ESG経営、海洋プラスチックごみ問題、サーキュラーエコノミーなど。
●宮原 伸朗 氏
2007年にアミタに合流後、環境管理リスクとコストを同時低減するシステムの導入支援、および企業へのコンサルティングに従事。その後、経営企画部門、新規事業開発のリーダーを経ながら、サーキュラーエコノミーの実践集団としてのコンソーシアム(J-CEP)の事務局を担当。2023年には内閣府が進める戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期の研究開発テーマ「自治体協力回収プラスチックの分別・供給システムの確立」の研究開発責任者を務め、2024年1月よりアミタホールディングス株式会社の執行役員に就任。
●久保 昌男 氏
2006年3月に大学(工学部機械工学科)卒業後、株式会社ヤクルト本社に入社。開発部に所属し、2016年まで生産技術・容器包装技術の開発に従事。2017年に部内異動により商品開発に携わることとなり、「蕃爽麗茶」や「ジョア」などを担当し、2021年発売の「Y1000」では新容器を開発。併行して、プラスチック容器包装における循環型経済への適応について検討を進めるなか、2022年4月に、現所属部署の前身となる環境対応推進室が新設され異動となり、以後、容器包装の資源循環について戦略立案や外部連携によるプロジェクト推進などを進め、現在に至る。
●井関 和人 氏
1991年神戸市入庁。区役所、産業振興局、行財政局、文化スポーツ局などを経て、2024年4月より現職。
【講演内容】
CLOMAはプラスチックの循環利用を推進しコミュニティや生活者とともに海洋プラごみのゼロ化を目指す企業アライアンスです。
セミナーでは神戸市にも参加してもらい、同市が進めるプラ回収に参画する企業との議論を通して官民連携の勘所や未来像につき議論を深めます。
【講演者プロフィール】
●柳田 康一 氏
1985年花王株式会社入社、加工プロセス研究室長、包装容器研究室長、サステナビリティ推進部長、ESG部門副統括を歴任、2019年からはCLOMA技術統括を担当し現在に至る。
専門分野は、トイレタリー製品の設計・製造、ユニバーサルデザイン、レスポンシブルケア、ESG経営、海洋プラスチックごみ問題、サーキュラーエコノミーなど。
●宮原 伸朗 氏
2007年にアミタに合流後、環境管理リスクとコストを同時低減するシステムの導入支援、および企業へのコンサルティングに従事。その後、経営企画部門、新規事業開発のリーダーを経ながら、サーキュラーエコノミーの実践集団としてのコンソーシアム(J-CEP)の事務局を担当。2023年には内閣府が進める戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期の研究開発テーマ「自治体協力回収プラスチックの分別・供給システムの確立」の研究開発責任者を務め、2024年1月よりアミタホールディングス株式会社の執行役員に就任。
●久保 昌男 氏
2006年3月に大学(工学部機械工学科)卒業後、株式会社ヤクルト本社に入社。開発部に所属し、2016年まで生産技術・容器包装技術の開発に従事。2017年に部内異動により商品開発に携わることとなり、「蕃爽麗茶」や「ジョア」などを担当し、2021年発売の「Y1000」では新容器を開発。併行して、プラスチック容器包装における循環型経済への適応について検討を進めるなか、2022年4月に、現所属部署の前身となる環境対応推進室が新設され異動となり、以後、容器包装の資源循環について戦略立案や外部連携によるプロジェクト推進などを進め、現在に至る。
●井関 和人 氏
1991年神戸市入庁。区役所、産業振興局、行財政局、文化スポーツ局などを経て、2024年4月より現職。
<モデレーター>

|
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局 技術統括 南部 博美 |

|

<パネリスト>

|
(株)セブン&アイ・ホールディングス ESG推進本部サステナビリティ推進部 シニアオフィサー 尾崎 一夫 |

|


|
三菱ケミカル(株) ベーシックマテリアルズ&ポリマーズビジネスグループ 戦略企画本部 CN・CE戦略部 部長 板東 健彦 |

|


|
三井物産(株) パフォーマンスマテリアルズ本部 サーキュラーエコノミー推進チーム 次長 道明 太郎 |

|

【講演内容】
日本のプラスチック資源循環を加速するためのキーとなるケミカルリサイクル技術の社会実装には様々な課題が存在する。CLOMAにおける商社、石油化学メーカー、リテーラーといった循環を構成するステークスホルダーを交えた議論により課題解決の方向性を探る。
【講演者プロフィール】
●南部 博美 氏
1988年 花王株式会社入社し、マテリアルサイエンス研究所 室長、副所長などを担当。
2023年9月にCLOMA出向し、2024年より現職に従事。
●尾崎 一夫 氏
1988年に(株)イトーヨーカ堂に入社。販売促進部マネジャー。
2006年に(株)セブン&アイ・ホールディングスへ転籍。社会・文化開発部オフィサー、CSR統括部環境担当オフィサー。
2020年より現職。
●板東 健彦 氏
1995年、三菱化学株式会社(現三菱ケミカル)に入社。海外子会社管理、経営企画室、海外プロジェクトなどの担当を経て、2022年より現職で廃プラスチックの油化、バイオマス原料化、CCUなどのプロジェクトに従事。
●道明 太郎 氏
1996年:早稲田大学理工学部応用化学科卒業。同年4月三井物産株式会社に入社。入社以来、化学品セグメントに従事。
2002年:英国ロンドン駐在。
2016年:本州化学工業(株)に出向。経営企画部副部長兼事業開発室長としてファインケミカルの新製品開発と新規事業開発を担当。
2019年:カーボンニュートラル水素関連の新規事業プロジェクト立ち上げ。
2022年:森林資源マーケティング室長として南米の森林資源事業開発(グリーンバイオプロジェクト)を担当。世界最大パルプメーカーと共同開発事業を手掛ける。
2024年:プラスチック資源循環による再資源化でサーキュラーエコノミー領域の新規事業創出と事業開発支援を担当。
【講演内容】
日本のプラスチック資源循環を加速するためのキーとなるケミカルリサイクル技術の社会実装には様々な課題が存在する。CLOMAにおける商社、石油化学メーカー、リテーラーといった循環を構成するステークスホルダーを交えた議論により課題解決の方向性を探る。
【講演者プロフィール】
●南部 博美 氏
1988年 花王株式会社入社し、マテリアルサイエンス研究所 室長、副所長などを担当。
2023年9月にCLOMA出向し、2024年より現職に従事。
●尾崎 一夫 氏
1988年に(株)イトーヨーカ堂に入社。販売促進部マネジャー。
2006年に(株)セブン&アイ・ホールディングスへ転籍。社会・文化開発部オフィサー、CSR統括部環境担当オフィサー。
2020年より現職。
●板東 健彦 氏
1995年、三菱化学株式会社(現三菱ケミカル)に入社。海外子会社管理、経営企画室、海外プロジェクトなどの担当を経て、2022年より現職で廃プラスチックの油化、バイオマス原料化、CCUなどのプロジェクトに従事。
●道明 太郎 氏
1996年:早稲田大学理工学部応用化学科卒業。同年4月三井物産株式会社に入社。入社以来、化学品セグメントに従事。
2002年:英国ロンドン駐在。
2016年:本州化学工業(株)に出向。経営企画部副部長兼事業開発室長としてファインケミカルの新製品開発と新規事業開発を担当。
2019年:カーボンニュートラル水素関連の新規事業プロジェクト立ち上げ。
2022年:森林資源マーケティング室長として南米の森林資源事業開発(グリーンバイオプロジェクト)を担当。世界最大パルプメーカーと共同開発事業を手掛ける。
2024年:プラスチック資源循環による再資源化でサーキュラーエコノミー領域の新規事業創出と事業開発支援を担当。
|
|
Aramco Asia Korea Ltd. Quality Management Manager, Quality Management Department Ali Mahdi Al-Yami |

|

【講演内容】
本講演では、サウジアラビアのAramco大規模プロジェクトにおける道路インフラに革命をもたらす再生プラスチックアスファルト(RPA)の革新的な利用について紹介する。世界的なプラスチックリサイクルの課題を概説し、RPAがプラスチック廃棄物とアスファルトの消費量を削減することでいかに持続可能な開発に貢献できるかを強調する。
【講演者プロフィール】
現在、ソウルのAramco Asia Koreaで品質管理マネージャーとして勤務し、Saudi Aramcoが承認した50社以上の韓国メーカーを担当している。
2012年から2024年までSaudi Aramcoに勤務していた。土木工学の専門家として著名な Al-Yami 氏は、サウジアラビアのキング・ファハド石油鉱物大学で理学士号を優秀な成績で取得し、米国のフロリダ大学で土木工学修士号(材料)を最優秀の成績で取得したほか、複数のリーダーシッププログラムを修了している。
石油、ガス、インフラ分野で10年以上の豊富な経験を持つAl-Yami氏は、2つのACI資格、リーンシックスシグマのブラックベルト、IRCA登録のQMS主任監査員資格など、いくつかの国際資格も保有している。
【講演内容】
本講演では、サウジアラビアのAramco大規模プロジェクトにおける道路インフラに革命をもたらす再生プラスチックアスファルト(RPA)の革新的な利用について紹介する。世界的なプラスチックリサイクルの課題を概説し、RPAがプラスチック廃棄物とアスファルトの消費量を削減することでいかに持続可能な開発に貢献できるかを強調する。
【講演者プロフィール】
現在、ソウルのAramco Asia Koreaで品質管理マネージャーとして勤務し、Saudi Aramcoが承認した50社以上の韓国メーカーを担当している。
2012年から2024年までSaudi Aramcoに勤務していた。土木工学の専門家として著名な Al-Yami 氏は、サウジアラビアのキング・ファハド石油鉱物大学で理学士号を優秀な成績で取得し、米国のフロリダ大学で土木工学修士号(材料)を最優秀の成績で取得したほか、複数のリーダーシッププログラムを修了している。
石油、ガス、インフラ分野で10年以上の豊富な経験を持つAl-Yami氏は、2つのACI資格、リーンシックスシグマのブラックベルト、IRCA登録のQMS主任監査員資格など、いくつかの国際資格も保有している。

|
(株)UACJ サステナビリティ推進本部 未来へ環境をつなぐ部 主幹 野瀬 健二 |

|

【講演内容】
アルミニウム素材はリサイクルの推進により、資源循環と温室効果ガス削減の両方が実現できる優れた素材である。このため様々な分野において、アルミの水平リサイクルの実現に向けた取り組みが加速している。本講演では、この分野における新たな技術や環境保証の動向を概説する。
【講演者プロフィール】
2007年、東京大学工学部マテリアル工学専攻にて博士(工学)を取得後、東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門にて助教に着任。2014年、UACJに入社後、R&Dセンター 研究企画室、サステナビリティ推進本部などを経て、現在はアルミ素材の環境保証の仕組み構築などに従事。業界団体での活動として日本アルミニウム協会 サーキュラーエコノミー企画委員、アルミ缶委員会技術WG長や国際アルミ連盟(IAI)のグローバル飲料缶循環アライアンス委員等を歴任し、現在に至る。
【講演内容】
アルミニウム素材はリサイクルの推進により、資源循環と温室効果ガス削減の両方が実現できる優れた素材である。このため様々な分野において、アルミの水平リサイクルの実現に向けた取り組みが加速している。本講演では、この分野における新たな技術や環境保証の動向を概説する。
【講演者プロフィール】
2007年、東京大学工学部マテリアル工学専攻にて博士(工学)を取得後、東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門にて助教に着任。2014年、UACJに入社後、R&Dセンター 研究企画室、サステナビリティ推進本部などを経て、現在はアルミ素材の環境保証の仕組み構築などに従事。業界団体での活動として日本アルミニウム協会 サーキュラーエコノミー企画委員、アルミ缶委員会技術WG長や国際アルミ連盟(IAI)のグローバル飲料缶循環アライアンス委員等を歴任し、現在に至る。

|
住友化学(株) エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所 環境負荷低減技術開発グループ グループマネージャー 森 康彦 |

|

【講演内容】
住友化学は、環境負荷の低減に貢献するSolution Providerとしての地位を確立することを目指し、化石資源の代替として使用済みプラスチックや二酸化炭素を原料とする炭素循環技術の開発を進めている。本報告では、この技術に関する触媒およびプロセスの開発状況について紹介する。
【講演者プロフィール】
1993年3月九州大学大学院工学研究科修了、住友化学株式会社に入社。工業化技術研究所にて新規プロセス開発や合理化検討に従事。2020年4月より、現エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所にてケミカルリサイクルやCCU技術に関する触媒とプロセス開発を担当し、現在に至る。
【講演内容】
住友化学は、環境負荷の低減に貢献するSolution Providerとしての地位を確立することを目指し、化石資源の代替として使用済みプラスチックや二酸化炭素を原料とする炭素循環技術の開発を進めている。本報告では、この技術に関する触媒およびプロセスの開発状況について紹介する。
【講演者プロフィール】
1993年3月九州大学大学院工学研究科修了、住友化学株式会社に入社。工業化技術研究所にて新規プロセス開発や合理化検討に従事。2020年4月より、現エッセンシャル&グリーンマテリアルズ研究所にてケミカルリサイクルやCCU技術に関する触媒とプロセス開発を担当し、現在に至る。
※3/18時点:講演タイトルが変更となりました。

|
東レ(株) 繊維研究所 所長 荒西 義高 |

|

【講演内容】
繊維産業においても、循環型社会構築に向けてサステナビリティ実現が重要な課題である。バイオマス由来原料の活用と共に、現状決して高いとは言えない繊維製品リサイクル率の向上が急務となっている。業界の動向もあわせ、東レ株式会社の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1994年3月、京都大学大学院農学研究科修士修了、東レ株式会社に入社。 繊維研究所合成繊維研究室に配属され、ポリエステル繊維、ポリ乳酸繊維、熱可塑性セルロース繊維などの研究に従事。2017年より繊維研究所所長。
【講演内容】
繊維産業においても、循環型社会構築に向けてサステナビリティ実現が重要な課題である。バイオマス由来原料の活用と共に、現状決して高いとは言えない繊維製品リサイクル率の向上が急務となっている。業界の動向もあわせ、東レ株式会社の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1994年3月、京都大学大学院農学研究科修士修了、東レ株式会社に入社。 繊維研究所合成繊維研究室に配属され、ポリエステル繊維、ポリ乳酸繊維、熱可塑性セルロース繊維などの研究に従事。2017年より繊維研究所所長。

|
協和産業(株) 代表取締役 安藤 太郎 |

|

【講演内容】
プラスチックリサイクルの現状や市場を取り巻く環境、顧客ニーズと事業者との認識格差、今後の市場展開等を自動車のプラスチックリサイクルを例にとり弊社の取り組み事例を含めてご紹介します。
【講演者プロフィール】
大学卒業後、三井物産プラハン株式会社(現三井物産プラスチック株式会社)に入社し三井物産株式会社に出向。
2004年、同社を退職し協和産業株式会社に入社し斯業経験を積み取締役を経て、
2007年3月代表取締役に就任し、現在に至る。
【講演内容】
プラスチックリサイクルの現状や市場を取り巻く環境、顧客ニーズと事業者との認識格差、今後の市場展開等を自動車のプラスチックリサイクルを例にとり弊社の取り組み事例を含めてご紹介します。
【講演者プロフィール】
大学卒業後、三井物産プラハン株式会社(現三井物産プラスチック株式会社)に入社し三井物産株式会社に出向。
2004年、同社を退職し協和産業株式会社に入社し斯業経験を積み取締役を経て、
2007年3月代表取締役に就任し、現在に至る。

|
三井化学(株) 研究開発本部 高分子・複合材料研究所 リサーチフェロー 伊崎 健晴 |

|

【講演内容】
三井化学では、サーキュラーエコノミ実現のためバイオマス戦略、リサイクル戦略に注力している。廃プラスチックの資源循環を実現するための取り組み、特にリサイクルプラスチックの品質安定化のための粘度均一化技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
1988年 三井東圧(株)入社、1997年 三井化学(合併による社名変更)、高分子レオロジー、成形加工、シミュレーションに従事し、2013年より リサーチフェロー、現職に至る。2020年よりリサイクルの研究に従事、長岡技術科学大学客員教授、2024年 金沢工業大学客員教授。2007年 日本レオロジー学会技術賞、2022年 高分子学会フェロー、2024年 日本レオロジー学会論文賞を受賞。
【講演内容】
三井化学では、サーキュラーエコノミ実現のためバイオマス戦略、リサイクル戦略に注力している。廃プラスチックの資源循環を実現するための取り組み、特にリサイクルプラスチックの品質安定化のための粘度均一化技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
1988年 三井東圧(株)入社、1997年 三井化学(合併による社名変更)、高分子レオロジー、成形加工、シミュレーションに従事し、2013年より リサーチフェロー、現職に至る。2020年よりリサイクルの研究に従事、長岡技術科学大学客員教授、2024年 金沢工業大学客員教授。2007年 日本レオロジー学会技術賞、2022年 高分子学会フェロー、2024年 日本レオロジー学会論文賞を受賞。

|
Sustainable Plastics Initiative (SusPla) 理事長 石塚 勝一 |

|

【講演内容】
循環経済への移行に伴い循環資源として再生プラスチック市場の健全な拡大が必要であります。SusPlaは本年4月に一般社団法人化し、再生プラスチックを取巻く全てのステークホルダー様と共に市場拡大のため積極的に課題解決に取り組んで参ります。
【講演者プロフィール】
再生プラスチックの製造販売を行っている石塚化学産業(株)に45年間勤め、昨年代表取締役会長に就任。その間、全日本プラスチックリサイクル工業会会長や関東プラスチックリサイクル協同組合理事長を努める。2018年に「心臓産業の会」を再生メーカー4社で立上げ、再生プラスチックを正しく知ってもらう活動を行い、2023年に(一社)サスティナブル経営推進機構様と再生プラスチックの適性評価に繋がるSPC(Sustainable Plastics Certification)認証制度の開発を発表。2024年7月に再生プラスチック市場の健全な発展を目指したSusPla(Sustainable Plastics Initiative)をステークホルダーと共に立上げ理事長に就任、本年4月に一般社団法人化。更なる循環経済移行を目指す。
【講演内容】
循環経済への移行に伴い循環資源として再生プラスチック市場の健全な拡大が必要であります。SusPlaは本年4月に一般社団法人化し、再生プラスチックを取巻く全てのステークホルダー様と共に市場拡大のため積極的に課題解決に取り組んで参ります。
【講演者プロフィール】
再生プラスチックの製造販売を行っている石塚化学産業(株)に45年間勤め、昨年代表取締役会長に就任。その間、全日本プラスチックリサイクル工業会会長や関東プラスチックリサイクル協同組合理事長を努める。2018年に「心臓産業の会」を再生メーカー4社で立上げ、再生プラスチックを正しく知ってもらう活動を行い、2023年に(一社)サスティナブル経営推進機構様と再生プラスチックの適性評価に繋がるSPC(Sustainable Plastics Certification)認証制度の開発を発表。2024年7月に再生プラスチック市場の健全な発展を目指したSusPla(Sustainable Plastics Initiative)をステークホルダーと共に立上げ理事長に就任、本年4月に一般社団法人化。更なる循環経済移行を目指す。

|
三菱電機(株) リサイクル共創センター 資源循環戦略エキスパート 井関 康人 |

|

【講演内容】
使用済み家電製品から回収した混合プラスチックから、高品位のPP、ABS、PSを分離回収する高度選別技術と家電製品への水平リサイクルについて説明する。また、家電リサイクルで長年培ったこの技術を、家電以外の領域のプラスチックへ展開するリサイクル共創センターの取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1996年より、三菱電機で、使用済み家電製品から金属やプラスチックを素材別に分離回収する高度選別技術開発および事業化に取り組み、2010年に家電混合プラスチックの選別・素材化事業を立ち上げる。2022年より、リサイクル共創センターにて、家電で長年培った高度選別技術を、家電以外の領域へ展開する新規事業創出に従事し現在に至る。
【講演内容】
使用済み家電製品から回収した混合プラスチックから、高品位のPP、ABS、PSを分離回収する高度選別技術と家電製品への水平リサイクルについて説明する。また、家電リサイクルで長年培ったこの技術を、家電以外の領域のプラスチックへ展開するリサイクル共創センターの取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1996年より、三菱電機で、使用済み家電製品から金属やプラスチックを素材別に分離回収する高度選別技術開発および事業化に取り組み、2010年に家電混合プラスチックの選別・素材化事業を立ち上げる。2022年より、リサイクル共創センターにて、家電で長年培った高度選別技術を、家電以外の領域へ展開する新規事業創出に従事し現在に至る。

|
国立大学法人広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 岡本 康寛 |

|

【講演内容】
レーザ微細加工の基礎的内容として「レーザ光と材料の相互作用」と「レーザ加工の基礎要素と種類」を説明した後,レーザ微細加工のアプリケーションとして講演者らが取り組んでいる除去加工,接合加工,表面改質法等,さらに近年の各種会議で報告されている研究内容より最新動向を紹介するとともに,今後の可能性に関しても述べる.
【講演者プロフィール】
1998年岡山大学大学院修士課程修了,同年岡山大学工学部助手,2004年大阪大学学位取得(博士(工学)),2006年フラウンホーファー・レーザ技術研究所およびアーヘン工科大学客員研究員,2013年より岡山大学准教授,2025年より広島大学教授を務める.レーザ微細加工,およびマイクロ加工の研究活動に従事し,これまでに査読論文101編,招待講演63件,国際会議プロシーディングス100編以上を発表するとともに,23件の特許を取得している.レーザ加工学会副会長,レーザ精密微細加工国際シンポジウムLPM議長,Editor of Journal of Laser Micro /Nanoengineering,Senior Editor of Journal of Laser Applications等も務める.
【講演内容】
レーザ微細加工の基礎的内容として「レーザ光と材料の相互作用」と「レーザ加工の基礎要素と種類」を説明した後,レーザ微細加工のアプリケーションとして講演者らが取り組んでいる除去加工,接合加工,表面改質法等,さらに近年の各種会議で報告されている研究内容より最新動向を紹介するとともに,今後の可能性に関しても述べる.
【講演者プロフィール】
1998年岡山大学大学院修士課程修了,同年岡山大学工学部助手,2004年大阪大学学位取得(博士(工学)),2006年フラウンホーファー・レーザ技術研究所およびアーヘン工科大学客員研究員,2013年より岡山大学准教授,2025年より広島大学教授を務める.レーザ微細加工,およびマイクロ加工の研究活動に従事し,これまでに査読論文101編,招待講演63件,国際会議プロシーディングス100編以上を発表するとともに,23件の特許を取得している.レーザ加工学会副会長,レーザ精密微細加工国際シンポジウムLPM議長,Editor of Journal of Laser Micro /Nanoengineering,Senior Editor of Journal of Laser Applications等も務める.

|
フォトンブレインジャパン 代表 家久 信明 |
|
【講演内容】
2μmの波長は、水や有機材料に対して高い吸収性を持っており、プラスチックやガラスの精密加工に適用されている。更に光ファイバー伝送も可能な事から医療分野では、内視鏡に搭載され組織の切断や凝固用途に適用が拡大している。また最近では、超先端半導体露光装置の励起光源として2μmレーザの研究が活発に行われている状況を紹介する。
【講演者プロフィール】
1979年3月慶応義塾大学工学部電気工学科卒
1979年4月~1986年3月:松下電器産業㈱
1986年3月~2000年12月:ファナック㈱
1990年12月、大阪大学基礎工学部より、「封止型CO2レーザーの長寿命化研究」により工学博士号取得。
2001年1月~2005年9月:㈱片岡製作所
2005年10月~2013年3月:ミヤチテクノス㈱
2013年4月〜フォトンブレインジャパン設立し、レーザーを応用した加工機の技術、市場動向調査、新規企画のコンサルティングビジネスを行っている。
2018年8月〜2022年8月信州大学繊維学部特任教授
2025年4月〜高知工科大学客員教授
【講演内容】
2μmの波長は、水や有機材料に対して高い吸収性を持っており、プラスチックやガラスの精密加工に適用されている。更に光ファイバー伝送も可能な事から医療分野では、内視鏡に搭載され組織の切断や凝固用途に適用が拡大している。また最近では、超先端半導体露光装置の励起光源として2μmレーザの研究が活発に行われている状況を紹介する。
【講演者プロフィール】
1979年3月慶応義塾大学工学部電気工学科卒
1979年4月~1986年3月:松下電器産業㈱
1986年3月~2000年12月:ファナック㈱
1990年12月、大阪大学基礎工学部より、「封止型CO2レーザーの長寿命化研究」により工学博士号取得。
2001年1月~2005年9月:㈱片岡製作所
2005年10月~2013年3月:ミヤチテクノス㈱
2013年4月〜フォトンブレインジャパン設立し、レーザーを応用した加工機の技術、市場動向調査、新規企画のコンサルティングビジネスを行っている。
2018年8月〜2022年8月信州大学繊維学部特任教授
2025年4月〜高知工科大学客員教授

|
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 情報・生産技術部 コーディネーター 森 清和 |

|

【講演内容】
レーザ加工などのものづくり技術へのAI(機械学習)の活用は急速に進んでいる。KISTECがNEDOプロでの成果をもとに、得たい品質となるロバスト加工条件を可視化できるAI条件推奨と,発光強度の周波数分布に注目し,異常の原因も推定できるAIモニタリング技術を報告する.
【講演者プロフィール】
1980年大阪大学卒業。日産自動車(株)入社。車体の生産技術開発に従事。自動車ボディのレーザ溶接と品質保証技術の開発を担当した。その後、光産業創成大学院大学、神奈川県立産業技術研究所において、レーザ加工へAI(機械学習)の応用を研究し、現在に至る。
【講演内容】
レーザ加工などのものづくり技術へのAI(機械学習)の活用は急速に進んでいる。KISTECがNEDOプロでの成果をもとに、得たい品質となるロバスト加工条件を可視化できるAI条件推奨と,発光強度の周波数分布に注目し,異常の原因も推定できるAIモニタリング技術を報告する.
【講演者プロフィール】
1980年大阪大学卒業。日産自動車(株)入社。車体の生産技術開発に従事。自動車ボディのレーザ溶接と品質保証技術の開発を担当した。その後、光産業創成大学院大学、神奈川県立産業技術研究所において、レーザ加工へAI(機械学習)の応用を研究し、現在に至る。

|
DMG森精機(株) AM部 執行役員 廣野 陽子 |
|
【講演内容】
Additive Manufacturing (AM)は、従来の方法では不可能であった形状や構造の実現を可能にし、製造業界に革命をもたらしている。本講演ではAMの量産部品への適用事例とともに、量産や生産現場のDX実現に必要な機能として開発した技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
2009年3月,京都大学大学院工学研究科マイクロエンジニアリング専攻精密計測加工学研究室を修了,三菱重工業株式会社に入社,工作機械等の開発に従事.2019年5月よりDMG森精機株式会社にてアディティブマニュファクチャリングを担当し,2022年より日本AM協会理事も拝命,2024年9月に京都大学大学院工学研究科にて博士(工学)を取得,2025年1月に執行役員に就任,現在に至る.
【講演内容】
Additive Manufacturing (AM)は、従来の方法では不可能であった形状や構造の実現を可能にし、製造業界に革命をもたらしている。本講演ではAMの量産部品への適用事例とともに、量産や生産現場のDX実現に必要な機能として開発した技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
2009年3月,京都大学大学院工学研究科マイクロエンジニアリング専攻精密計測加工学研究室を修了,三菱重工業株式会社に入社,工作機械等の開発に従事.2019年5月よりDMG森精機株式会社にてアディティブマニュファクチャリングを担当し,2022年より日本AM協会理事も拝命,2024年9月に京都大学大学院工学研究科にて博士(工学)を取得,2025年1月に執行役員に就任,現在に至る.
<モデレーター>

|
(株)ナ・デックス 技術センター 技術統括フェロー/大阪大学 名誉教授 片山 聖二 |

|

<パネリスト>

|
レーザーライン(株) 代表取締役社長 武田 晋 |

|


|
(株)デンソー 生産革新センター 先進プロセス研究部 Project General Manager 白井 秀彰 |

|


|
トヨタ自動車(株) 電池製造技術部 機能・モノづくり開発室 プロフェッショナルパートナー 佐藤 彰生 |

|


|
日産自動車(株) 生産技術研究開発センター エキスパートリーダー 樽井 大志 |

|

【講演内容】
世界的な気候変動問題の解決に向けたカーボンニュートラルへの取り組みが進む中、自動車産業も大きな変革期を迎え、その製造に関してレーザ加工の導入が重要な役割になると期待されている。本講演では、自動車製造におけるレーザ加工のエキスパ-ト(レーザ発振器、パワートレイン、車体、コンポーネント)をパネリストに迎えレーザ加工の現状や今後の展望・期待についてディスカッションを行う。
【講演者プロフィール】
●片山 聖二 氏
約35年間、大阪大学の溶接工学研究所・接合科学研究所において、助手、助教授および教授として、レーザ溶接およびレーザ加工の研究に従事。
定年退職後、100 kWのファイバレーザ装置を有するナデックスレーザR&Dセンターにおいてセンター長として勤務し、研究開発指導。
●武田 晋 氏
日本大学工学部工業化学科(現・物質化学工学科)卒業。丸文(株)入社、エキシマレーザから高出力半導体レーザまで世界各国の最先端レーザ機器販売に従事。2007年にジェイディーエスユニフェーズ(株)の日本統括マネージャーに就く。CCOP事業部にて産業用レーザ及び光通信用オプティカルコンポーネントを担当、同社加工用高出力ファイバーレーザの開発を進める。2011年に同社代表取締役、2015年にルーメンタム(株)代表取締役を経て、2017年 レーザーライン(株)代表取締役社長に就任。現在に至る。レーザー輸入振興協会理事、中部レーザ応用技術研究会副会長、光産業創生大学院大学レーザによるものづくり中核人材育成講座講師
●白井 秀彰 氏
日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社後、生産技術開発部門に配属し、一貫して接合分野における技術開発業務を担当し、新しい加工プロセスの創出と技術開発を進めレーザ加工、抵抗溶接、アーク溶接など幅広い領域で多岐に亘り開発技術を立ち上げ自動車部品生産ラインでの実用化に成功し、現在は、先進プロセス研究部Project General Managerとして新しい領域での新技術創成に尽力している。
レーザ加工学会理事、溶接学会東海支部商議委員,中部レーザー応用技術研究会顧問、博士(工学)
●佐藤 彰生 氏
1988年トヨタ自動車入社以来、生産技術の開発部に所属し、レーザを用いたアプリケーション開発に携わってきた。レーザクラッド、焼き入れ、微細加工などの技術開発を通し主にエンジン部品など実用化。2017年開発したレーザクラッドバルブシートはトヨタのTNGAエンジンに広く採用され、高い燃費性能と出力を両立し、HEVエンジンに搭載されている。この間、NEDO様、ALPROT様のレーザ加工技術研究会委員や中部レーザ応用研究会様の幹事長など担当した。近年はCNに貢献するレーザ加工開発を担当し現在に至る。
●樽井 大志 氏
91年3月大阪大学大学院工学部卒
同年4月 日産自動車入社,技術開発センターに配属され,車体のレーザ溶接TWB技術開発を担当.
93~97年 日産自動車 材料研究所に移り レーザ溶接の基礎研究を行う.
98年以降 技術開発センターに戻り 車体のレーザ溶接(ルーフ部,連続溶接)の開発を行う.2000年以降はレーザ溶接のほか,アルミの機械的接合技術開発など車体の接合技術開発全般を担当する.
2008~2011年 電気自動車の初代リーフのバッテリー工場の立ち上げを行い
2011年以降は 再び 現在の生産技術研究開発センターに帰任し,2014年以降はエキスパートリーダーとしてて車体の接合技術開発全般を担当している
【講演内容】
世界的な気候変動問題の解決に向けたカーボンニュートラルへの取り組みが進む中、自動車産業も大きな変革期を迎え、その製造に関してレーザ加工の導入が重要な役割になると期待されている。本講演では、自動車製造におけるレーザ加工のエキスパ-ト(レーザ発振器、パワートレイン、車体、コンポーネント)をパネリストに迎えレーザ加工の現状や今後の展望・期待についてディスカッションを行う。
【講演者プロフィール】
●片山 聖二 氏
約35年間、大阪大学の溶接工学研究所・接合科学研究所において、助手、助教授および教授として、レーザ溶接およびレーザ加工の研究に従事。
定年退職後、100 kWのファイバレーザ装置を有するナデックスレーザR&Dセンターにおいてセンター長として勤務し、研究開発指導。
●武田 晋 氏
日本大学工学部工業化学科(現・物質化学工学科)卒業。丸文(株)入社、エキシマレーザから高出力半導体レーザまで世界各国の最先端レーザ機器販売に従事。2007年にジェイディーエスユニフェーズ(株)の日本統括マネージャーに就く。CCOP事業部にて産業用レーザ及び光通信用オプティカルコンポーネントを担当、同社加工用高出力ファイバーレーザの開発を進める。2011年に同社代表取締役、2015年にルーメンタム(株)代表取締役を経て、2017年 レーザーライン(株)代表取締役社長に就任。現在に至る。レーザー輸入振興協会理事、中部レーザ応用技術研究会副会長、光産業創生大学院大学レーザによるものづくり中核人材育成講座講師
●白井 秀彰 氏
日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社後、生産技術開発部門に配属し、一貫して接合分野における技術開発業務を担当し、新しい加工プロセスの創出と技術開発を進めレーザ加工、抵抗溶接、アーク溶接など幅広い領域で多岐に亘り開発技術を立ち上げ自動車部品生産ラインでの実用化に成功し、現在は、先進プロセス研究部Project General Managerとして新しい領域での新技術創成に尽力している。
レーザ加工学会理事、溶接学会東海支部商議委員,中部レーザー応用技術研究会顧問、博士(工学)
●佐藤 彰生 氏
1988年トヨタ自動車入社以来、生産技術の開発部に所属し、レーザを用いたアプリケーション開発に携わってきた。レーザクラッド、焼き入れ、微細加工などの技術開発を通し主にエンジン部品など実用化。2017年開発したレーザクラッドバルブシートはトヨタのTNGAエンジンに広く採用され、高い燃費性能と出力を両立し、HEVエンジンに搭載されている。この間、NEDO様、ALPROT様のレーザ加工技術研究会委員や中部レーザ応用研究会様の幹事長など担当した。近年はCNに貢献するレーザ加工開発を担当し現在に至る。
●樽井 大志 氏
91年3月大阪大学大学院工学部卒
同年4月 日産自動車入社,技術開発センターに配属され,車体のレーザ溶接TWB技術開発を担当.
93~97年 日産自動車 材料研究所に移り レーザ溶接の基礎研究を行う.
98年以降 技術開発センターに戻り 車体のレーザ溶接(ルーフ部,連続溶接)の開発を行う.2000年以降はレーザ溶接のほか,アルミの機械的接合技術開発など車体の接合技術開発全般を担当する.
2008~2011年 電気自動車の初代リーフのバッテリー工場の立ち上げを行い
2011年以降は 再び 現在の生産技術研究開発センターに帰任し,2014年以降はエキスパートリーダーとしてて車体の接合技術開発全般を担当している

|
(株)村田製作所 プリンシパルリサーチャー 上田 英樹 |
|
【講演内容】
ミリ波帯では,伝送損失が大きいという課題を克服するためアンテナ一体型モジュール(AiM)が用いられる.また,ミリ波通信の普及に向けた課題の一つに低コスト化が挙げられる.アンテナパフォーマンスと低コスト化を両立する村田製作所独自の技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
2010年3月,東京工業大学大学院 博士課程修了.同大学院 特別研究員を経て,2011年4月,株式会社村田製作所に入社.RF-MEMSの開発を経て,2013年4月より現部門に所属.ミリ波モジュールの主にアンテナ技術開発統括を担当し,現在に至る.
【講演内容】
ミリ波帯では,伝送損失が大きいという課題を克服するためアンテナ一体型モジュール(AiM)が用いられる.また,ミリ波通信の普及に向けた課題の一つに低コスト化が挙げられる.アンテナパフォーマンスと低コスト化を両立する村田製作所独自の技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
2010年3月,東京工業大学大学院 博士課程修了.同大学院 特別研究員を経て,2011年4月,株式会社村田製作所に入社.RF-MEMSの開発を経て,2013年4月より現部門に所属.ミリ波モジュールの主にアンテナ技術開発統括を担当し,現在に至る.

|
日本製鉄 (株) 技術開発本部技術開発企画部研究戦略室 室長 有田 吉宏 |

|

【講演内容】
カーボンニュートラルに向けた鉄鋼業界の取り組みにつき、革新的な製鉄プロセスの技術開発動向を中心に、リサイクル、副生物、エネルギー問題等に触れ、さらに鉄鋼製品によるカーボンニュートラル社会実現への貢献について述べる。
【講演者プロフィール】
1995年大阪大学大学院修士課程修了、新日本製鐵入社。2012年まで電磁鋼板の技術開発に従事。その後、研究企画業務を経て、現在に至る。
【講演内容】
カーボンニュートラルに向けた鉄鋼業界の取り組みにつき、革新的な製鉄プロセスの技術開発動向を中心に、リサイクル、副生物、エネルギー問題等に触れ、さらに鉄鋼製品によるカーボンニュートラル社会実現への貢献について述べる。
【講演者プロフィール】
1995年大阪大学大学院修士課程修了、新日本製鐵入社。2012年まで電磁鋼板の技術開発に従事。その後、研究企画業務を経て、現在に至る。

|
大同特殊鋼(株) 機能製品事業部 帯鋼製品部 帯鋼技術サービス室 室長 石川 浩一 |
|
【講演内容】
グリーン社会の実現にむけてモビリティの電動化は拡大しており、搭載されるセンサ・スイッチ・抵抗器などの電子部品の使用も増加している。電子部品は高機能化・小型化が進んでおり、本講演では、性能向上に貢献する軟磁性材料、封着材料など機能材料について紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年4月 大同特殊鋼株式会社に入社。
技術開発研究所にてステンレス鋼や機能材料の開発に従事。
2023年より現部署にて新商品の企画、開発、技術サービスを担当。
【講演内容】
グリーン社会の実現にむけてモビリティの電動化は拡大しており、搭載されるセンサ・スイッチ・抵抗器などの電子部品の使用も増加している。電子部品は高機能化・小型化が進んでおり、本講演では、性能向上に貢献する軟磁性材料、封着材料など機能材料について紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年4月 大同特殊鋼株式会社に入社。
技術開発研究所にてステンレス鋼や機能材料の開発に従事。
2023年より現部署にて新商品の企画、開発、技術サービスを担当。
受講券の発行方法をお選びください。